高等学校における生命倫理教育に関する教材開発
Change in high school student attitudes to biotechnology in response to teaching materials
岡武志,メイサーダリル Takeshi Oka and Darryl Macer
筑波大学生物科学系 Institute of Biological Sciences, University of Tsukuba
Email: takesi@ruby.ocn.ne.jp, asianbioethics@yahoo.co.nz
pp. 92-97 in 日本における高校での生命倫理教育、メイサー ダリル(編)、ユウバイオス倫理研究会 2000年。
1. はじめに
遺伝子組換えなどに代表されるバイオテクノロジーの近年のめまぐるしい発展は,医療技術や農業,製薬などの様々な分野で大きな進歩をもたらし,社会的に多大な影響を与えつつある。この新たな技術の発展の中で,今までの倫理観では対応しきれない多くの問題やジレンマが生じてきている。先進技術を使うことが,無条件に良いことにつながるとは限らない。つまり,「出来ることを無制限に実行すること」が本当に良いことなのかどうかの判断が難しくなっているのである。
このような現状をふまえて,生命科学技術と社会や一般市民の理解とが遊離しないような新たな生命倫理(バイオエシックス)を理科(生物)の授業で扱う必要性があると考えられる。生命倫理とは,生命科学や医療技術の進歩にともなって数多く生じてきた,生命観や人間の生死に関わる倫理的な問題や,価値観に関わる問題などを扱うために生まれた学問体系のことを指す。また生命倫理を理科教育で扱う意義としては,理科教育,特に生物教育の中で,科学の応用面を取り上げたり,科学,技術と社会との相互作用を意識した授業を行うとすれば,どうしても生命倫理に関わる問題を避けて通ることはできないことがあげられている。また,さらに大学の医学・生物学分野の学部・学科に進学しない限りは,生命倫理的な問題やそれを理解するための知識について勉強する機会はほとんどないと考えられる。従って多くの人々にとって,このような問題に対処できる基礎的な能力を持つことができるのは,高校での生物の授業が最後の機会であると考えられる。しかしながら,日本においては,生命科学の知識や技術について教える優れた実践はあるものの,倫理的問題に重点を置いた教材の開発はほとんど見られないことも指摘されている。
そこで本研究では,多角的な視野から生命倫理的問題について考えることのできる能力を生徒達に身につけさせられるような,生命倫理的問題に重点を置いた教材の開発を目的とする。
2. 研究目的
高等学校生物において,生命倫理的問題に重点を置いた教材を開発し,その試行と評価を行う。
3. 研究方法
1)生命倫理的問題を取り扱った,日本や海外の理科教育に関する先行研究調査を行う。またこの調査などをもとに,生命倫理を理科教育において取り上げることの意義について述べる。
2)高等学校生物における生命倫理の位置づけを調べるために,学習指導要領,学習指導要領解説及び教科書の分析を行う。
3)以上より得られた調査,分析の結果をふまえて,理科(生物)教育において用いることができるような教材を作成する。
4)作成した教材を用いて実際に試行授業を行い,結果を分析し,改良点などを考察する。
4. 論文の概要
1) 先行研究の文献調査
教材開発にあたり,生命倫理を授業で扱っている先行研究の調査を行った。その結果,科学教育において生命倫理を扱う目的としては,価値の明確化,意思決定能力の育成があげられていた。また,価値教育としての位置づけがあげられていた。Barman(1980)は,科学教育における,科学によって生み出された問題や価値を扱った教育の必要性を挙げている。その理由としてBarmanは,科学は社会に大きな影響を与える様々な問題や価値を人々に投げかけてきており,科学から生み出される価値や問題は,これからもさらに増えていくことが考えられるからであると述べている。そしてBarmanは,科学教育における価値教育について4つのアプローチを提示しており,その1つに「道徳的発達(Moral Development)」というものをあげている。この主な目的は,道徳的価値葛藤(モラルジレンマ)を通して生徒の道徳性・倫理性の発達を助けることであり,これは,Kohlbergの理論をもとにしている。
Kohlbergは道徳性の発達段階の理論を提唱しており,モラルジレンマを生じさせることによって価値を明確化させ,葛藤を通して倫理性や道徳性の発達がみられることを述べている。またこの「道徳性」とは,何が正しいかによって行動するといった行動の内に求めるのでなく,何が善で,正しいかを判断するその理由付けの中に生起する,とみなしている。そして,道徳性が発達するというのは道徳的な判断や推論,つまり道徳的な認識が変化することとしている。この道徳性の発達には,認知能力と役割取得能力の二つの能力の発達とが結びついているとしている。その認知能力とは世界を知り,自分と世界との間の適応をはかる知的な能力のことであり,役割取得能力は自分の考えや気持ちと同時に他者の考えや気持ちを受け入れ,調整する能力を言うとしている。そして,この認知能力の発達は,自分と世界との間に生じた矛盾や疑問といった不均衡な状態を,生徒自らが行う自己調整によって解消することによって達せられる。これはPiagetの認知発達理論に基づいており,自分と世界との間に生じた矛盾や疑問,つまりモラルジレンマを生徒に与えることによって,認知能力の発達が促され,さらに道徳性の発達が促されるとされている。
また近年,教育の中で生命尊重の態度の育成の必要性が高まっている。第15期中央教育審議会第1次答申で示された「生きる力」のように,生命尊重の態度や心の育成が求められている。また,高等学校理科の学習指導要領解説の中でも,生命尊重の態度の育成が理科教育の目標の一つに挙げられており,生命倫理的問題やそこから生じるモラルジレンマを教材に取り入れていくことによって,効果的にこの要請に応えられることが考えられる。
2) 教材の作成
何を教材の題材にするかを決めるにあったって,倫理的な問題を含む点,ジレンマを生じさせる点,生徒の興味,関心を引き出す点などをふまえ,題材としては動物工場とクローン技術について取り扱うことにした。以下に本教材の目的を示す。
「生命倫理的な問題について気づき,その問題から生命とは何かということを深く考え,そしてその問題について客観的な判断のできる市民の育成」
またこの目的は以下の4つの目標からなる。
「動物工場とクローン技術を理解する上で必要となる,基礎的な分子生物学の概念を理解し,説明することができる」
「動物工場とクローン技術の基礎的な内容について,科学的に説明することができる」
「科学的な概念や知識をふまえた上で,倫理的な問題について考え,客観的に自分の考えを表すことができる」
「生命を尊重する態度の育成」
このうち,「基礎的な分子生物学の概念を理解し,説明することができる」については,既に授業で扱われていたので,評価の対象に入れなかった。
次に,本教材の題材として取り上げた動物工場とクローン技術の利点,欠点,問題点について示す。
○動物工場の利点
・希少なタンパク質を大量に効率よく得ることができる。
・絶対的に不足している移植用臓器を補うことができる。
○動物工場の問題点
・移植した臓器が異種間で正常に機能するのかどうか。
・動物中に存在する未知のウイルスが,人体に悪影響を及ぼす可能性。
・動物をどこまで操作して良いのかという倫理的な問題。
○クローン技術の利点
・品質の良い家畜を大量に生み出すことがでる。
・遺伝子を導入したトランスジェニック家畜(動物工場)を効率よく増やすことができる。
・希少動物の保護や復活への応用。
○クローン技術の問題点
・遺伝情報が同じなので生物の多様性がなくなる。
・不妊症などの解決のためヒトへの応用が理論的には可能となるといった倫理的問題点。
このような,動物工場,クローン技術の利点・欠点をふまえ,両面から捉えたプリントやビデオなどの教材を作成した。また本研究では,プレテスト・ポストテストを一つの教材とみなし,ここでBarmanが述べているモラルジレンマを提示した。
また,動物工場とクローン技術を教材化するために,これらの内容を理解するのに必要な概念と高校生物教科書との対応を調べた。この内,クローン技術,拒否反応といった教科書には対応していない概念については,基本を押さえて内容を絞り込み,教材ではなるべく優しく理解しやすいものにすることを心掛けた。
3) 試行授業の結果及び考察
・試行授業及びその評価について
作成した教材を用いた試行授業は,茨城県内の公立高校の選択生物(生物_,選択人数24人)の授業において行われた。またこの教材の評価については,試行授業前後に行ったプレテスト・ポストテストの比較,授業後に行ったワークシート及び事後アンケートの分析を行った。
・試行授業の結果と考察
以下に,試行授業によって得られた主な結果について示す。
1 プレテスト・ポストテストの分析
この分析は,試行授業の前後での回答及びそれに対する理由の変化を中心に行った。
・問3 ヒトに適合する心臓を,ブタに作らせることにあなたは,
(1)賛成(2)やや賛成(3)やや反対(4)反対 (5)わからない
図1. 問3におけるプレテスト・ポストテストの回答の比較
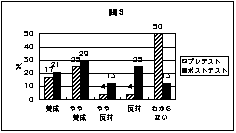
図1.に示す通り,試行授業後には「わからない」が減少し,「反対」の増加がみられた。回答に対して書かれた理由の内容をもとにこの変化を分析してみると,知識や情報不足により「わからない」を選択していた生徒が,試行授業後に動物工場とクローン技術の情報を得ることによって判断を行い,「わからない」から「反対」に移行したことが見られた。
また,回答に対して書かれた理由の内容を見ていくと試行授業後に「人の都合でブタを殺してはいけない。」「ブタを殺してまで生きたくはない,生命を軽視している。」「他の種を作り変えてはいけない。」という理由が見られた。これは生物を尊び大切にする心や,人間だけでなくすべての生き物は同等の価値を持つといった,生命尊重に対する一つの考えを自己の中に生み出した表れであり,多様な視点から生命をとらえられ,生命尊重の態度が深まったと考えられる。
・問11 クローン技術の良い面や悪い面について,知っていることを書いて下さい。
また,問11はクローン技術の利点・欠点といった両面性について質問している。得られた自由記述の回答を一定の尺度により評価し,プレテスト・ポストテストで比較した。比較はχ2検定によって行った。検定の結果,良い面・悪い面の両面を認識した生徒の増加に有意差が認められた(χ2 (2)=25.620, p < .01)。
2 ワークシートの分析
このワークシートでは,クローン技術・動物工場の知識及び,利点・欠点の両面についてを設問している。結果,すべての問において,ほとんどの生徒がクローン技術または動物工場の内容に関して正しく記述できていた。また,動物工場・クローン技術の利点・欠点についても,両面から正しくとらえ記述できていた。よって,これらのことから,「動物工場とクローン技術の基礎的な内容について,科学的に説明することができる」という教材の目標が達成されたと考えられる。また,動物工場・クローン技術の利点・欠点を正しくとらえられるようになったことは,これらの問題を両面からとらえ客観的に判断できる基礎ができたと考えられる。
3 事後アンケートの分析
ここでは,授業後に行った教材内容に関するアンケートの結果を分析した。各問ともに「非常にそう思う」,「少しそう思う」,「どちらでもない」,「あまりそう思わない」,「非常にそう思わない」の5段階の評定法により回答を得た。これをもとに,問ごとの各評価を選択した人数と,回答者総数に対する割合をパーセントで表し,それをグラフ化した。その結果の一部を図2.に示す。
また,事後アンケートの回答分布を「肯定的な意見」「どちらでもない」「否定的な意見」の3つに分類し,1試料によるχ2検定を行った。この結果,「今回の授業内容に興味は持てましたか?」「今回のような授業は必要だと思いますか?」「プリントはわかりやすかったですか?」などいくつかの問において有意差が見られ,「肯定的な意見」に回答の分布が偏っていることが示された。
図2. 授業後のアンケート結果(N=24)
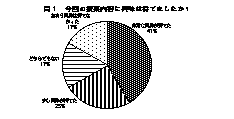 4) 結論
プレテスト・ポストテスト,ワークシート及び事後アンケートの分析を通して,以下の結論を得ることができた。
○試行授業後に否定的な意見が増加する傾向が見られた。
これは主に,「わからない」をプレテストで選択していた人が,ポストテストでは否定的な意見を選択したことによる。これは,客観性がまだ十分に発達してないためや,情報の明確化による影響などが考えられる。
○動物工場とクローン技術について科学的に説明することができるようになった。
動物工場とクローン技術の内容についての科学的説明と,これらの良い面・悪い面について試行授業後に正しく記述できるようになった。これは教材の目標の一つであり,この目標は本教材によって達成された。
○生命尊重につながる意見が見られるようになった。
人間中心的な視点からだけではなく,動物の権利を表すような発言が見られるようになった。これは,生命を多様な視点からとらえられるようになったことを表し,生命尊重の態度の深まりにつながることが考えられる。また試行授業後には,生物を尊び大切にすることや,生き物はすべて等しい価値を持つといった意見も見られるようになった。よって,本教材の目標「生命を尊重する態度の育成」は達成することができた。また,これは道徳的価値葛藤(モラルジレンマ)が「生命を尊重する態度の育成」に有効であることを示している。
○動物工場やクローン技術を多面的にとらえた意見が見られるようになった。
試行授業後には,判断基準の明確化が見られた。また,利点や問題点といった物事を両面からとらえた意見や,人の意見もふまえられた,より客観的な意見も見られるようになった。よって教材の目標である,「倫理的な問題について,科学的な概念をふまえた上で,客観的に自分の考えを表すことができる」は達成されたと言える。
5. 今後の課題
生命尊重につながるであろう意見の表れも見られたが,試行授業の出席者全員に生命尊重の態度が見られたわけではなかった。よって,今後モラルジレンマの内容を物語形式にするといった工夫が必要であると考えられる。
また,回答に対する明確な理由付けができた生徒も全員ではなかった。これを改善していくためには,情報収集の過程や発表,討論の時間を授業に導入していく必要性が考えられる。
4) 結論
プレテスト・ポストテスト,ワークシート及び事後アンケートの分析を通して,以下の結論を得ることができた。
○試行授業後に否定的な意見が増加する傾向が見られた。
これは主に,「わからない」をプレテストで選択していた人が,ポストテストでは否定的な意見を選択したことによる。これは,客観性がまだ十分に発達してないためや,情報の明確化による影響などが考えられる。
○動物工場とクローン技術について科学的に説明することができるようになった。
動物工場とクローン技術の内容についての科学的説明と,これらの良い面・悪い面について試行授業後に正しく記述できるようになった。これは教材の目標の一つであり,この目標は本教材によって達成された。
○生命尊重につながる意見が見られるようになった。
人間中心的な視点からだけではなく,動物の権利を表すような発言が見られるようになった。これは,生命を多様な視点からとらえられるようになったことを表し,生命尊重の態度の深まりにつながることが考えられる。また試行授業後には,生物を尊び大切にすることや,生き物はすべて等しい価値を持つといった意見も見られるようになった。よって,本教材の目標「生命を尊重する態度の育成」は達成することができた。また,これは道徳的価値葛藤(モラルジレンマ)が「生命を尊重する態度の育成」に有効であることを示している。
○動物工場やクローン技術を多面的にとらえた意見が見られるようになった。
試行授業後には,判断基準の明確化が見られた。また,利点や問題点といった物事を両面からとらえた意見や,人の意見もふまえられた,より客観的な意見も見られるようになった。よって教材の目標である,「倫理的な問題について,科学的な概念をふまえた上で,客観的に自分の考えを表すことができる」は達成されたと言える。
5. 今後の課題
生命尊重につながるであろう意見の表れも見られたが,試行授業の出席者全員に生命尊重の態度が見られたわけではなかった。よって,今後モラルジレンマの内容を物語形式にするといった工夫が必要であると考えられる。
また,回答に対する明確な理由付けができた生徒も全員ではなかった。これを改善していくためには,情報収集の過程や発表,討論の時間を授業に導入していく必要性が考えられる。
6. 主要参考文献
Barman C. R. (1980), Four values education approaches for science teaching, The American Biology Teacher, 42, 152-156.
I. Wilmut, A. E. Schnieke, J. McWhir, A. J. Kind & K. H. S. Campbell (1997), Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells., Nature 385, 810-813.
R. P. ランツァ, D. K. C. クーパー, W. L. チック著/辻公美, 萩原政夫訳 (1997),「ここまで来た異種移植」,『日経サイエンス』, Vol. 27, No. 10, pp. 62-69.
W. H. ベランダー, H. ルボン, W. N. ドロハン著/西義助訳 (1997),「製薬工場としてのトランスジェニック家畜」, 『日経サイエンス』, Vol. 27, No. 4, PP. 78-84.
梅埜國夫 (1995),「生命倫理」,『理科の教育』, Vol. 44, No. 4, p. 23.
小川正賢 (1993),『序説 STS教育-市民のための科学技術教育とは-』, 東洋館出版社
佐野安仁, 吉田謙二編 (1993), 『コールバーグ理論の基底』, 世界思想社
Please send comments to
Email <
Macer@biol.tsukuba.ac.jp >.
日本における高校での生命倫理教育、メイサー ダリル(編)、ユウバイオス倫理研究会 2000年
学校における生命倫理教育ネットワーク
ユウバイオス倫理研究会(http://eubios.info/indexJ.html)
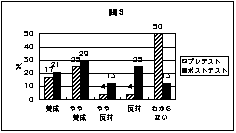
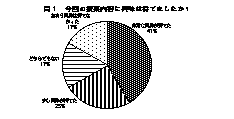 4) 結論
プレテスト・ポストテスト,ワークシート及び事後アンケートの分析を通して,以下の結論を得ることができた。
○試行授業後に否定的な意見が増加する傾向が見られた。
これは主に,「わからない」をプレテストで選択していた人が,ポストテストでは否定的な意見を選択したことによる。これは,客観性がまだ十分に発達してないためや,情報の明確化による影響などが考えられる。
○動物工場とクローン技術について科学的に説明することができるようになった。
動物工場とクローン技術の内容についての科学的説明と,これらの良い面・悪い面について試行授業後に正しく記述できるようになった。これは教材の目標の一つであり,この目標は本教材によって達成された。
○生命尊重につながる意見が見られるようになった。
人間中心的な視点からだけではなく,動物の権利を表すような発言が見られるようになった。これは,生命を多様な視点からとらえられるようになったことを表し,生命尊重の態度の深まりにつながることが考えられる。また試行授業後には,生物を尊び大切にすることや,生き物はすべて等しい価値を持つといった意見も見られるようになった。よって,本教材の目標「生命を尊重する態度の育成」は達成することができた。また,これは道徳的価値葛藤(モラルジレンマ)が「生命を尊重する態度の育成」に有効であることを示している。
○動物工場やクローン技術を多面的にとらえた意見が見られるようになった。
試行授業後には,判断基準の明確化が見られた。また,利点や問題点といった物事を両面からとらえた意見や,人の意見もふまえられた,より客観的な意見も見られるようになった。よって教材の目標である,「倫理的な問題について,科学的な概念をふまえた上で,客観的に自分の考えを表すことができる」は達成されたと言える。
5. 今後の課題
生命尊重につながるであろう意見の表れも見られたが,試行授業の出席者全員に生命尊重の態度が見られたわけではなかった。よって,今後モラルジレンマの内容を物語形式にするといった工夫が必要であると考えられる。
また,回答に対する明確な理由付けができた生徒も全員ではなかった。これを改善していくためには,情報収集の過程や発表,討論の時間を授業に導入していく必要性が考えられる。
4) 結論
プレテスト・ポストテスト,ワークシート及び事後アンケートの分析を通して,以下の結論を得ることができた。
○試行授業後に否定的な意見が増加する傾向が見られた。
これは主に,「わからない」をプレテストで選択していた人が,ポストテストでは否定的な意見を選択したことによる。これは,客観性がまだ十分に発達してないためや,情報の明確化による影響などが考えられる。
○動物工場とクローン技術について科学的に説明することができるようになった。
動物工場とクローン技術の内容についての科学的説明と,これらの良い面・悪い面について試行授業後に正しく記述できるようになった。これは教材の目標の一つであり,この目標は本教材によって達成された。
○生命尊重につながる意見が見られるようになった。
人間中心的な視点からだけではなく,動物の権利を表すような発言が見られるようになった。これは,生命を多様な視点からとらえられるようになったことを表し,生命尊重の態度の深まりにつながることが考えられる。また試行授業後には,生物を尊び大切にすることや,生き物はすべて等しい価値を持つといった意見も見られるようになった。よって,本教材の目標「生命を尊重する態度の育成」は達成することができた。また,これは道徳的価値葛藤(モラルジレンマ)が「生命を尊重する態度の育成」に有効であることを示している。
○動物工場やクローン技術を多面的にとらえた意見が見られるようになった。
試行授業後には,判断基準の明確化が見られた。また,利点や問題点といった物事を両面からとらえた意見や,人の意見もふまえられた,より客観的な意見も見られるようになった。よって教材の目標である,「倫理的な問題について,科学的な概念をふまえた上で,客観的に自分の考えを表すことができる」は達成されたと言える。
5. 今後の課題
生命尊重につながるであろう意見の表れも見られたが,試行授業の出席者全員に生命尊重の態度が見られたわけではなかった。よって,今後モラルジレンマの内容を物語形式にするといった工夫が必要であると考えられる。
また,回答に対する明確な理由付けができた生徒も全員ではなかった。これを改善していくためには,情報収集の過程や発表,討論の時間を授業に導入していく必要性が考えられる。